自己啓発本マイスターのハナハナです。
今回は、【トヨタ式】工場・オフィスの「整頓術」とは?】を、本:『[図解]トヨタの片づけ』を基に紹介します。
「整頓」の意味から、具体的な方法まで分かりやすく丁寧に解説していきます。
・オフィス、工場内を整頓したい
・整頓の意味を知りたい
・トヨタ式整頓術を取り入れたい
トヨタ式「整頓」とは?
整頓の定義
「何が」「いつ」「どのくらい」必要なのかを定めることが重要
本:『[図解]トヨタの片づけ』より
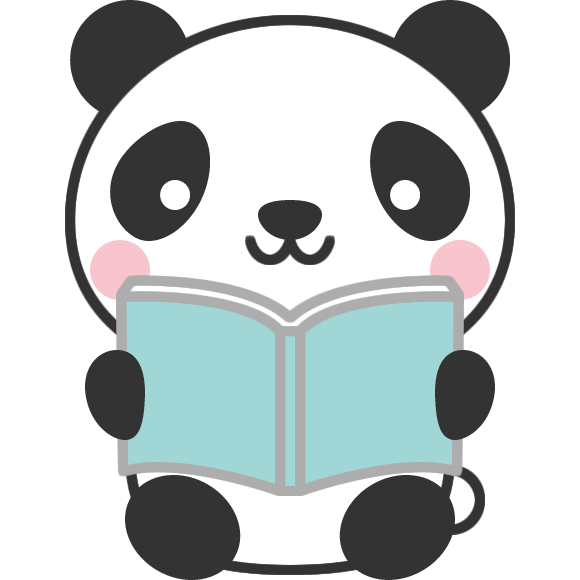
「5S」の2番目の活動だね。
まずは、トヨタ式「整頓」の定義について紹介致します。
必要なものを必要なときに必要なだけ取り出せるようにすること。
トヨタでは、職場環境の維持改善に「5S」というスローガンを掲げています。
具体的には、整理、整頓、清掃、清潔、しつけの5項目の頭文字「S」をまとめたものです。
第一段階の整理によって、「いるもの」と「いらないもの」を分けて、ゴミや使う予定の無いものを処分すると、「いるもの」だけが手元に残ります。
今回紹介する整頓では、「いるもの」を必要なときに必要なだけ取り出せるための、配置や置き方、考え方を学んでいきます。
トヨタ式「整理」と、トヨタが5Sを重視する目的は以下の記事で解説しています。


"必要なものを必要なときに必要なだけ取り出せるようにする"と言われても、多くの人は何から手を付ければいいか分からないと思います。
まずは、「何が」「いつ」「どのくらい」必要なのかを考えてみましょう。
自分の日々の行動を思い出して、思い出せない場合はこれから記録します。
それらが曖昧なまま整理を進めても、効率的な配置を決めることは出来ません。
何となくで整理を進めると、結局使い勝手の悪い非効率な配置になり、整頓のための整頓になってしまいます。
少し面倒臭いですが、トヨタ式「整頓」を進める上で非常に重要な工程です。
整頓で付随作業を0にする
パソコンに文章を打ち込むのが主作業で、必要な資料を取り出したり、プリントアウトしたりするのは付随作業です。
本:『[図解]トヨタの片づけ』より
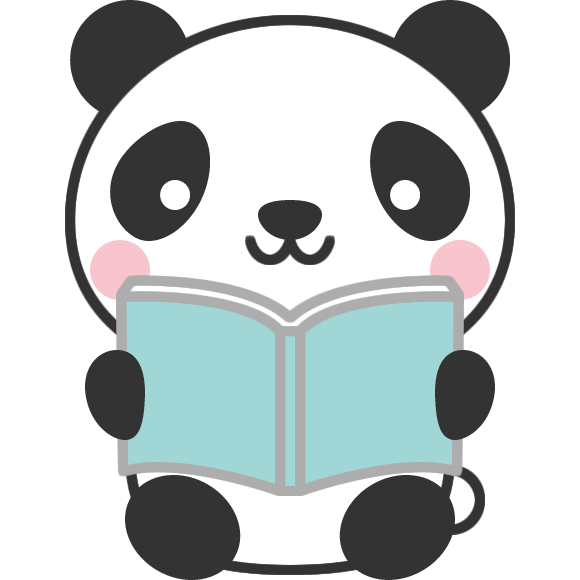
付随作業はものの配置で効率化できるんだね。
整頓を進める時には、「付随作業を0にするには?」という考え方をしてみましょう。
人の行動には、大きく分けて「主作業」と「付随作業」の2種類があります。
◼️「主作業」
⇨直接的に仕事を進行させる作業。
・工場の組み立て・・加工や組立など。
・オフィスの事務・・パソコンで文章を打ち込むなど。
◼️「付随作業」
⇨主作業を進行させるために、その前後や途中に必要な作業。
・工場の組み立て・・部品を準備する、完成品を出荷置き場に運搬するなど。
・オフィスの事務・・資料を取り出す、プリントアウトするなど。
主作業を減らすには、ある程度の時間や労力が掛かりますが、付随作業はものの配置を変えるだけで減らすことができます。
「主作業」と「付随作業」という分類を知っているだけでも、効率的なものの配置、効果的な整頓の発想ができるようになりますので、ぜひ頭に入れておきたい考え方です。
トヨタ式「整頓」実践編
使用頻度で分ける
「必要なもの」を、「頻度」にしたがって分類して、それぞれの置き場を考えます
本:『[図解]トヨタの片づけ』より
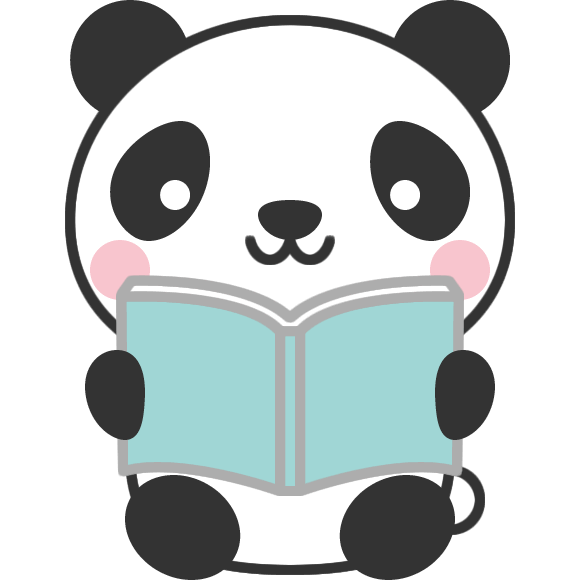
近くに置けばいいってことじゃ無いんだね。
ものの配置を使用頻度別に分けていきます。
本:『トヨタの片付け』では、使用頻度別に以下のように分類する方法が紹介されています。
①よく使うもの
⇨デスクの引き出しや近くの棚に置く。
②1週間〜1か月に1度使うもの
⇨少し離れた棚やロッカーに置く。
③数ヶ月〜1年に一度使うもの
⇨別室の資料室や倉庫に置く。
使用頻度が低いものを、デスクや近くの棚に置いておくと、毎日使うものが取り出しにくくなったり、置き場が溢れてしまいます。
逆に、使用頻度が高いのに別室の倉庫などに置いておくと、時間のロスが大きくなります。
整頓をする時は、使用頻度を見極めて適切な配置を考えていきましょう。
トヨタでは、作業者のワキが空かずに取れる所に、工具や部品が配置されているそうです。
そういう細かい所まで整頓が徹底されているとは、さすが世界のトヨタですよね。
共用品は置き場を絞る
置く場所をできるかぎり絞り込めば、使ったあとに必ず元に戻しますし、大事に使います。
本:『[図解]トヨタの片づけ』より
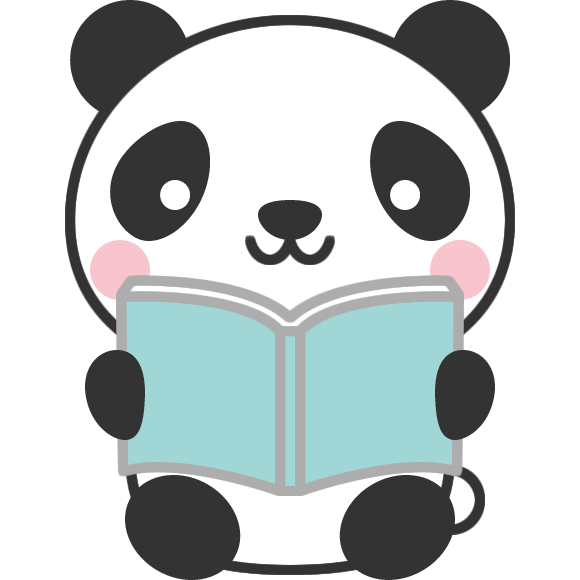
確かに、一箇所にまとめた方が分かりやすいよね。
共用品は置き場を絞り、出来るだけ一箇所にまとめておきましょう。
共用品の置き場が複数あると、探すのに手間取って無駄な時間が掛かってしまいます。
また、戻す時にも置き場が一箇所の方が分かりやすく、置き場によって共用品が無いということも防げます。
管理面でも、一箇所の置き場を確認すれば済むので楽です。
使用頻度が高いものは、個人で管理してもいいですが、数日に1回程度の頻度であれば、共用品は一箇所にまとめるのが原則です。
定位置を決めて明示する
不特定多数の人が使うものについては、定位置を決め、必ずそこに戻すということが必要不可欠です。
本:『[図解]トヨタの片づけ』より
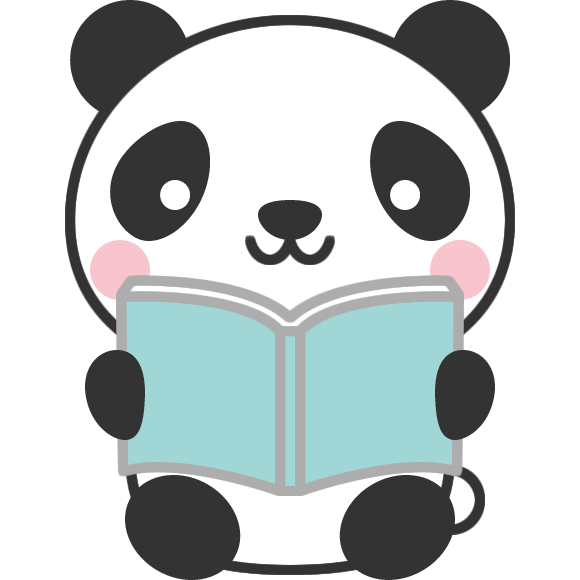
使ったら、元の状態に戻せることが大事なんだね。
整頓をする時は、必ず定位置を決めて明示し、元の位置に戻せるようにします。
ものの定位置が決まっていないと、何となくで新たなものが置かれ、時間が経つにつれ散らかってきます。
トヨタには、「姿置き」と呼ばれるものの形を表示して、表示と同じように置く方法もあるそうです。
最初はそこまで徹底できないと思いますので、まずは区画線を一本引いて、仮の基準をつくるなどして、定位置を決めます。
それを元にすれば、ものがそこに置かれている状態が、正常なのか異常なのか判断できるようになります。
明示は誰にでも分かるように大きく、自然に目に飛び込んでくることを意識しましょう。
動線を考える
トヨタの人間は「動線」といっていますが、これをチェックしてみるのです。
本:『[図解]トヨタの片づけ』より
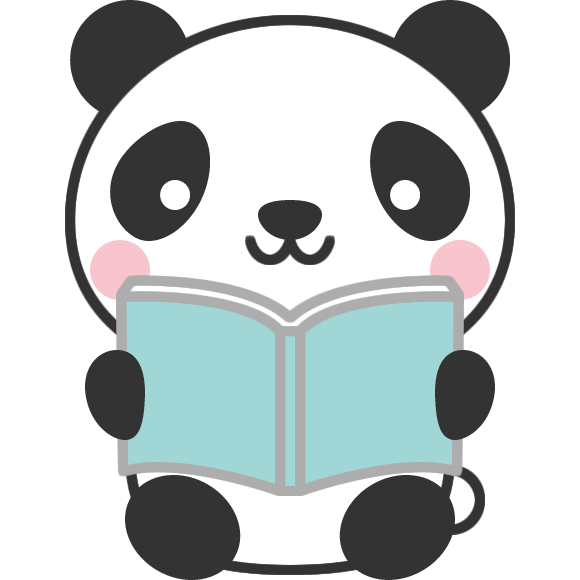
人の動きに合わせて、ものを配置すればいいんだね。
ものを使う人の動線を意識して、配置を決めていきましょう。
例えば、工場で加工作業をする時に、工具が離れた倉庫に置いてあったら時間の無駄ですよね。
原則として、動作と置き場所はセットと考えるようにすると無駄が減ります。
トヨタでは、ものの置き場所がマップ図に記されて、現場に掲示してあるそうです。
マップ図の中で、「○丁目○番地」のように住所を定めて、ものを使う人の動線を書き込んでみます。
そうすると、「工具と加工場の位置が離れすぎているから、○丁目○番地に場所を移そう」というように、使う人の動線を「見える化」し、具体的なアクションを起こすことができるのです。
おわりに
今回は、【トヨタ式】工場・オフィスの「整頓術」とは?】を、本:『[図解]トヨタの片づけ』を基に紹介しました。
皆さんの職場でも、取り入れられそうな内容はあったでしょうか?
本:『[図解]トヨタの片づけ』で紹介されているような、職場環境改善については、企業のノウハウですのであまり表に出てくることはありません。
そういう意味でも、本:『[図解]トヨタの片づけ』の内容は非常に貴重で、個人的にも参考になる部分が多かったです。
私が今回紹介させて頂いたのは、本の中の一部分だけですので、もっと詳しく知りたい方は、ぜひ本を読むことをオススメします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
☆この記事が参考になった方は、以下のブログランキングバナーをクリックして頂けると嬉しいです☆⬇︎
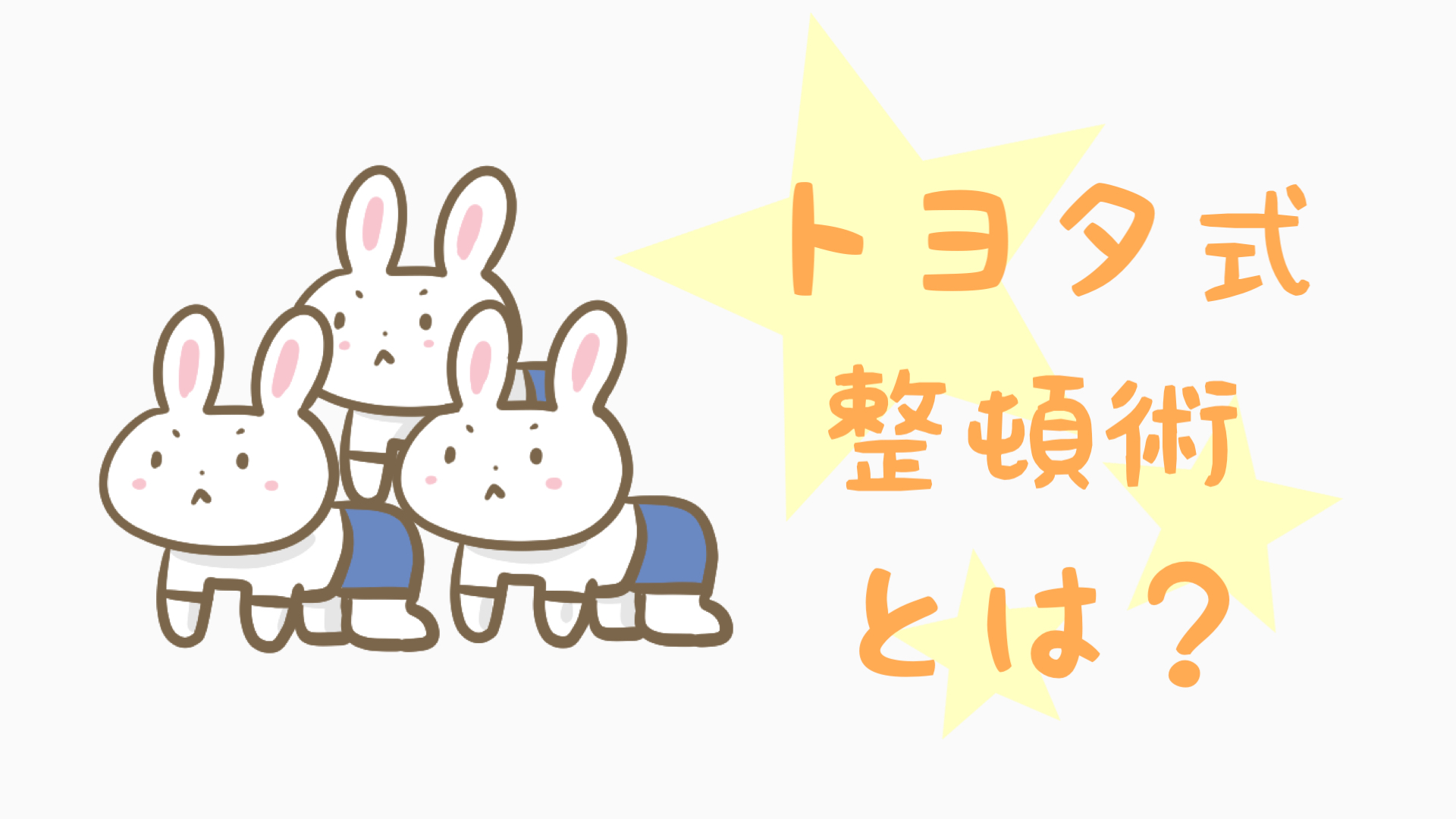



コメント